子どもの誤飲事故による中毒事例を想定した「模擬訓練」を実施しました
掲載日:2025年9月5日
地方衛生研究所(地衛研)は、地域で集団感染や大規模な食中毒などの「健康危機事象」が発生した際に、保健所や医療機関、他の府県や政令市の地衛研、国の各機関などと連携して、迅速かつ正確に対応する役割を担っています。
こうした背景から、近畿地方の地衛研は、化学物質・細菌・ウイルスが原因となる健康危機事象を想定した訓練(模擬訓練)を毎年実施し、健康危機事象への対応力を高めています。
令和6年度は、大阪健康安全基盤研究所が中心となり、子どもの誤飲事故による中毒事例を想定した「模擬訓練」を実施しました。ここでは、その取り組み内容を紹介します。
今回の模擬訓練には、近畿地方の13機関が参加しました。なお、結果の報告期限を当日の午後5時とし、7時間以内に原因物質を特定する設定としました。

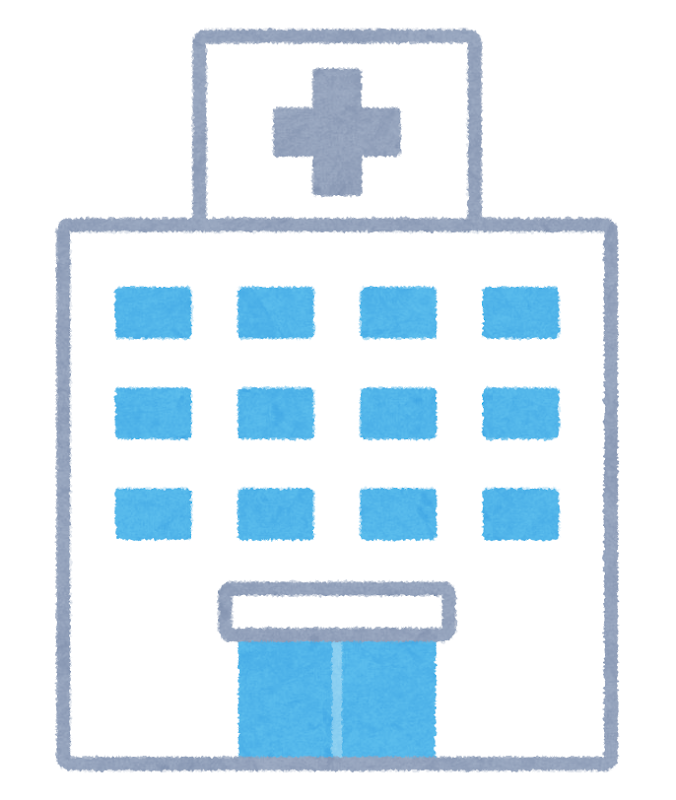
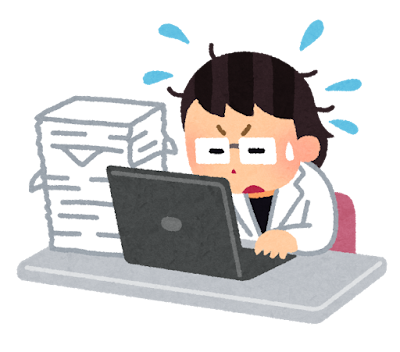

20××年10月×日 16時:地衛研に、保健所から下記の連絡が入る。
<事例1>
【第2報】(午前10時に参加機関へ公開)
20××年10月×日 18時30分:保健所から、同じ医療機関で農薬中毒が疑われる患者の報告があったと、連絡があった。
<事例2>
〔調査内容〕
〔保健所からの依頼〕
症状や喫食状況から、スポーツドリンクに農薬が含まれている可能性がある。スポーツドリンクを検査して、農薬の特定および濃度の測定をお願いしたい。
食品への農薬混入事件や誤飲事故は後を絶ちません(参考資料1、2)。これからも、このような模擬訓練を重ね、健康危機事象が発生した際に迅速かつ的確に対応できるよう、知識・技術・経験を蓄積し、地衛研の使命を果たしていきます。


こうした背景から、近畿地方の地衛研は、化学物質・細菌・ウイルスが原因となる健康危機事象を想定した訓練(模擬訓練)を毎年実施し、健康危機事象への対応力を高めています。
令和6年度は、大阪健康安全基盤研究所が中心となり、子どもの誤飲事故による中毒事例を想定した「模擬訓練」を実施しました。ここでは、その取り組み内容を紹介します。
模擬訓練とは?
担当機関が、健康被害を想定したシナリオを作成し、その内容に合わせた模擬試料(実際の検査に使う試料に似せたもの)を作ります。参加機関は、シナリオの情報から原因を推測し、試料を分析して原因を特定します。今回の模擬訓練には、近畿地方の13機関が参加しました。なお、結果の報告期限を当日の午後5時とし、7時間以内に原因物質を特定する設定としました。

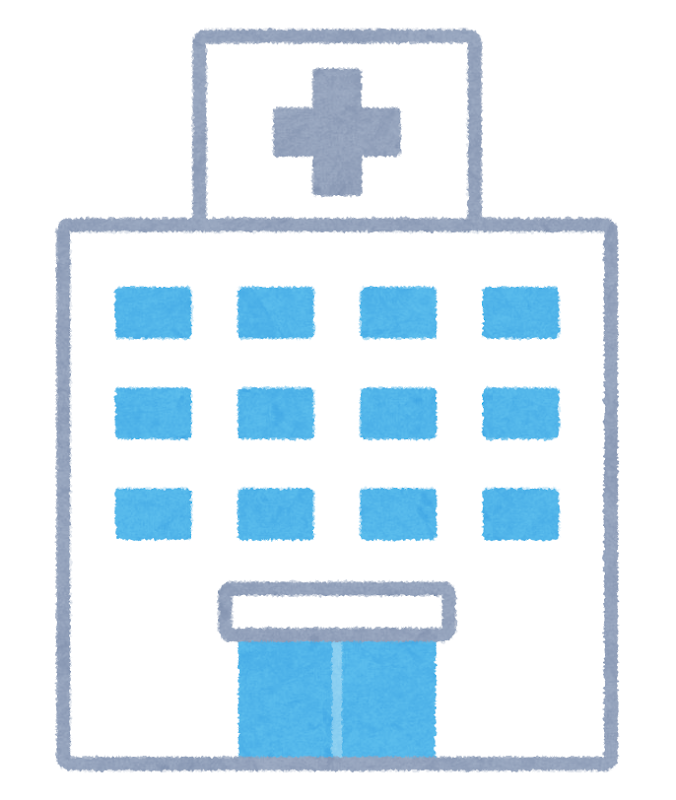
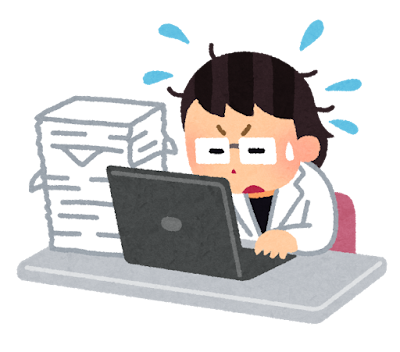

スケジュールとシナリオ
【第1報】(午前9時30分に参加機関へ公開)20××年10月×日 16時:地衛研に、保健所から下記の連絡が入る。
<事例1>
- 医療機関から、嘔吐、腹痛を訴えた患者2名を診察したとの連絡があった。
- 患者は13歳と11歳の兄弟であった。
- 家族とともに公園で市販の弁当を食べており、医師は食中毒を疑っている。
- 吐物、汚物などの検体の確保を依頼しており、搬入の可能性がある。
- 患者の行動内容や食事の内容、時間などは、現在調査中である。
【第2報】(午前10時に参加機関へ公開)
20××年10月×日 18時30分:保健所から、同じ医療機関で農薬中毒が疑われる患者の報告があったと、連絡があった。
<事例2>
- 患者は、6歳の男児で、<事例1>の兄弟であった。
- 嘔吐による脱水症状があり、救急搬送された。軽度の縮瞳(瞳孔が縮まる症状)が見られたため、農薬中毒の疑いで報告された。
〔調査内容〕
- 家族5人(<事例1>の13歳児と11歳児、<事例2>の6歳児、両親)は公園で遊び、園内で弁当を食べた。
- 弁当は市販のものを購入し、12時頃に家族全員で食べた。
- 子どもたちだけがスポーツドリンクを飲んだ。
- 13歳児と11歳児は14時頃から腹痛、嘔吐の症状を訴えていた。6歳児は17時頃より嘔吐の症状があった。
- 両親は無症状であった。
- 13歳児と11歳児は昼食時にスポーツドリンクをコップ(150 mL)で飲んだ。6歳児は15時頃に残っていたスポーツドリンクをコップ(200 mL)で飲んだ。
- スポーツドリンクは、子ども3人で前日に空の500 mLペットボトルを使用して、粉末の製品を水に溶かして作り、冷蔵庫で冷やしていたものであった。
- 使用したペットボトルは、勝手口に置いてあったものを6歳児が持ってきた。
- 家族はりんご園を営む農家であった。
- りんごに使用する農薬を希釈するために、空のペットボトルを使用していた。
〔保健所からの依頼〕
症状や喫食状況から、スポーツドリンクに農薬が含まれている可能性がある。スポーツドリンクを検査して、農薬の特定および濃度の測定をお願いしたい。
模擬訓練の結果
参加機関は、【第1報】と【第2報】の情報を元に、模擬試料の分析を行いました。その結果、原因となった有機リン系農薬を全ての機関が特定することができました。特定の手がかりとなったのは、【第2報】に記載された「りんごの栽培に使用される農薬」という情報に加え、「軽度の縮瞳」という症状です。この「縮瞳」とは眼の瞳孔(黒目の中央の部分)が通常より小さく収縮した状態を指し、有機リン系農薬による中毒で特徴的にみられる症状です。このように、原因物質の特定のためには、保健所や医療機関からの情報提供が欠かせず、これらの機関との連携が非常に重要です。食品への農薬混入事件や誤飲事故は後を絶ちません(参考資料1、2)。これからも、このような模擬訓練を重ね、健康危機事象が発生した際に迅速かつ的確に対応できるよう、知識・技術・経験を蓄積し、地衛研の使命を果たしていきます。


参考資料
- 令和5年度農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について:農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/250228.html - 乳幼児の窒息や誤飲に注意!:東京消防庁ホームページ
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/nichijo/children_tissoku.html
お問い合わせ
衛生化学部 食品化学課
電話番号:06-6972-1325
電話番号:06-6972-1325
