沿革・環境科学研究所時代
1974年から2006年(昭和49年から現在)
庁舎移転 所名改称
市民生活を取り巻く環境の悪化に対し、万全の調査研究体制をとるため、昭和49年12月、大阪市立環境科学研究所と改称し、庁舎を天王寺区東上町に新築し、機構および機能を強化しました。GC/MS、X線回折装置など大型機器や電子計算機の導入、ならびに分析技術課を設置し、所全体の分析機能のシステム化をはかりました。また、図書室を公開としました。

開所式後、所内施設を見学する大島市長
蓄積性化学物質への対応
BHC、DDTやPCBなどの有機塩素系化学物質は、難分解性で、生体に取り込まれた場合、排泄されにくく、河川の底泥や魚介類などに濃縮・蓄積することから、それらの使用が禁止されました。しかし、環境中に長く残留することが予想され、環境中の有機塩素系化学物質の調査に取り組みました。
増え続ける廃棄物処理への対応
年々増大する「ごみ」問題について、海面埋立処分場では、殺虫剤や覆土方法の開発によるハエ対策の提案により大きな効果をあげました。また、処分場の浸出水の監視及び排水処理方法の研究についても先駆的な研究として大きな成果をあげています。
国内でコレラ発生
昭和52年には、和歌山県で渡航歴のないコレラ患者が発生し、大量の魚介類や野菜類の検査を実施するとともに、その応援のため現地に研究員を派遣しました。その後、市内河川についてのコレラ菌の調査研究を開始しました。
アスベスト調査始める
昭和52年には、アスベストの環境濃度の調査を始めました。
バイオテクノロジーの導入
急速に発展した遺伝子工学技術を研究所業務に導入し、新たな展開をはかるため、昭和59年にバイオテクノロジーの基本的、応用的な検討を行うため、プロジェクトチームが結成され、研究体制の整備が行われました。その後、環境保全、感染症の迅速な原因究明及び分子疫学的解析、遺伝子組み換え食品の分析など、積極的に新技術の導入をはかりました。
大幅な機構改革
昭和63年に、企画調整課の新設など「環境保健行政の変化に即応した研究所のありかた」に基づいた機構改革、平成13年には環境部門の再編成があり現在に至っています。
ダイオキシン類問題、環境ホルモン問題
焼却工場からのダイオキシン類や魚介類のコプラナーPCB、化学物質による内分泌かく乱作用(いわゆる環境ホルモン問題)など微量化学物質の健康影響が明らかになりました。その現状把握と対策が求められ、食品、環境の各分野が協力して調査研究に取り組んでいます。
健康危機発生時における広域連携
大規模な食中毒など健康危機発生時には、関係部局と一体となって研究所の総力をあげて取り組んでいます。また、平成18年8月、近畿を中心とする2府7県の地方衛生研究所を有する17自治体は、新型感染症、毒劇物などによる健康危機発生の際、発生自治体の研究所のみでは対応が困難な場合に備え、地域を越えた連携をするための協定を締結しました。
感染症対策
大阪市では、結核罹患率が高いことから、当所においても、結核菌の分子疫学的調査など行政と一体となった取り組みを行っています。その他の感染症についても、大阪市感染症発生動向調査事業の一端を担い、発生予測、発生時の対策に寄与しています。
食品の安全性
食品の残留農薬、食品添加物、汚染物質などの調査を関係部局と一体となって、行っています。平成9年には検査の信頼性を確保するためのシステム(GLP)を導入しました。また、平成18年5月末から施行された残留農薬や動物用医薬品のポジティブリスト制への対応を進めて
機能性食品関係事業
平成15年度から、本市の健康予防医療分野における都市再生の一環として、産学官ネットワークによる特定保健用食品等の機能性食品開発に関する事業を推進しています。平成16年度から、特定保健用食品等の許可(承認)試験の登録試験機関としての業務をはじめました。
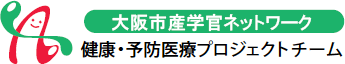
国際交流、貢献
これまで、JICA専門家として、インドネシア、メキシコ、チリ、タイ、チュニジア、ベトナムなどに研究員を派遣しました。また、「大気汚染防止」、「都市廃棄物」、「環境管理」などの研修コースに研究員が講師として参加し、当所が有する技術の発展途上国への移転、情報交換を中心に国際交流、貢献をはかってきました。

JICA研修風景
お問い合わせ
電話番号:06-6972-1321
